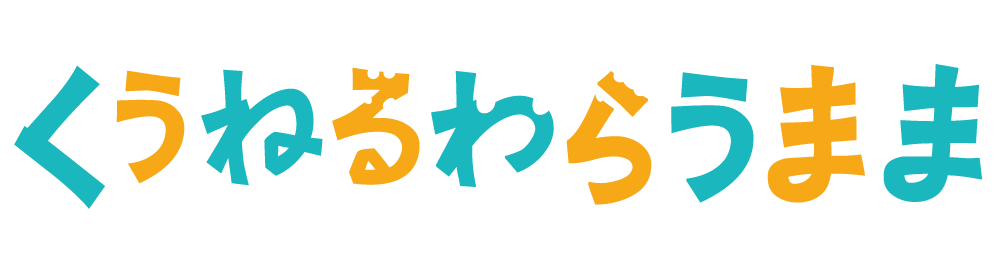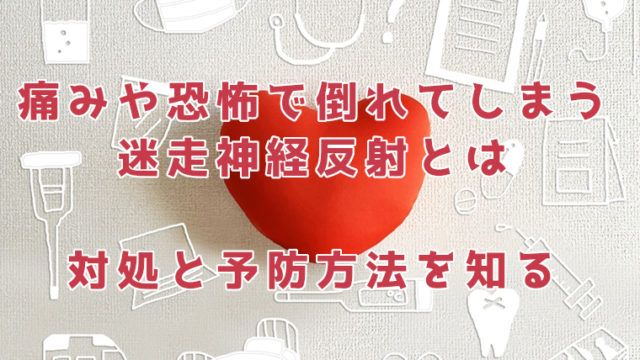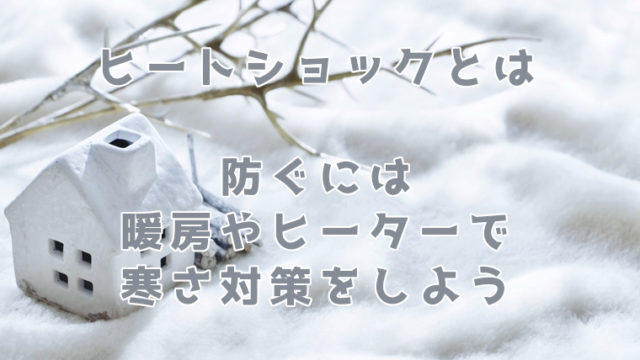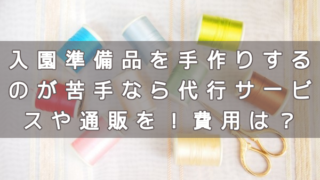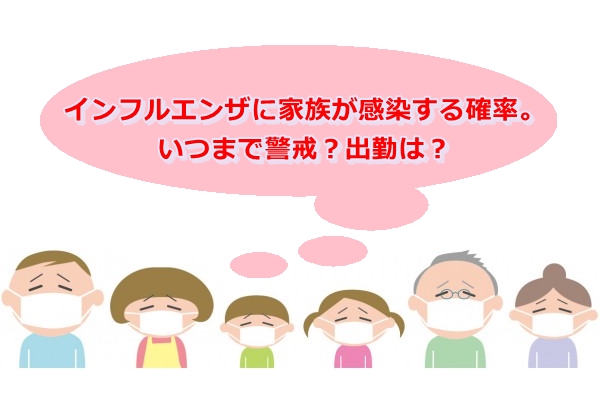
こんにちは、らひ子(@rhkcha)です。
家族の誰かがインフルエンザに感染した場合、一緒に暮らす家族はどうしたらいいでしょうか。
主婦からすると、夫や子供がインフルエンザにかかってしまったら、どう対応すればいいのか悩みますね。
自分までもがインフルエンザになってしまったら、看病する人がいなくなってしまい大変!
ここでは、インフルエンザを発症した家族を看病するときの注意や、家庭内での感染を防ぐ方法、仕事をしている場合はどうするのかを説明します。
インフルエンザが家族に感染し発症する確率は?
「感染」と「発症」の違い
感染……インフルエンザウイルスを保菌しているだけで、症状が出ていない状態
発症……インフルエンザウイルスが鼻や喉の粘膜内で増殖し、発熱をはじめとした症状が出た状態
よく聞くのが「家族がインフルエンザにかかったけど、自分はかからなかった」という状況。
これはもしかすると「家族がインフルエンザにかかって、自分もインフルエンザに感染したけど、体力と免疫力があるから発症はしなかった」ということかもしれません。
この場合、インフルエンザ特有の発熱や関節痛が出なかっただけで、インフルエンザウイルスを保菌している可能性があります。
インフルエンザにかかった家族がいても、その他の家族が発症するかしないかは、体力や免疫力が関係してくるので、一概に「発症する確率は○○%」ということはできません。
インフルエンザを発症した家族の看病をする時の注意
インフルエンザの家族を看病をするときに気をつけることを挙げていきます。
以下の点を守ることで、だいぶ感染しづらくなると思います。
インフルエンザの発症(発熱など)は、鼻や口から入ったインフルエンザウイルスが体内で増殖するからです。
粘膜である目からも感染することがあるので、看病中やその直後は、自分の顔を触らないように気をつけましょう。
感染予防には、やはりできるだけ患者が他の家族と接触を持たないようにすることが望ましいです。
トイレなど共用のものはある程度仕方ないですが、上記のことを心がけるだけで、だいぶ感染の危険性は減らせます。
ただし、患者が子どもの場合は、部屋にずっと寝かせていると様子が心配ですし、子供からの要求も色々あると思うので、できる範囲の隔離にしてください。
高熱が出て苦しいときに、子供が疎外感を感じて寂しがることのないよう、小学校高学年以上ならきちんと理由を話ししてあげましょう。
インフルエンザの家族内感染はいつまで警戒する?
家族の中の誰かが発熱しインフルエンザと診断されてから、他の家族にうつるとすると、ちょうど2日後に発症することが多いです。
例)1月1日に子供が発熱してインフルエンザと診断、1月3日に父親が発熱によりインフルエンザ発症
一般的に2~5日以内に周りの人に感染し、発症すると言われています。
わが家の場合は、子供がインフルエンザを発症すると、家族内の誰かが発症するまで、毎回きっちり2日後となっています。
夫や子供を看病することになったら、2日目の朝からは特に自分の体調に気を配りましょう。
前項「インフルエンザを発症した家族の看病をする時の注意」でも説明していますが、看病をする時にはウイルスに感染しないよう十分注意します。
そのうえで、万が一感染しても発症を防げるよう、看病する自分も栄養をしっかり摂り、寝不足に気をつけ、体を冷やさないことを心がけて、体力と免疫状態を良好に保つようにしましょう。
病は気から、という言葉もあるように、「インフルエンザがうつるかも……」と神経質になりすぎると、本当に具合が悪くなることもあります。
家族の看病は大変だと思いますが、あまり根を詰めないようにしてくださいね。
インフルエンザの家族がいる場合、会社への出勤はどうする?
家族(身近な人)がインフルエンザを発症した場合の対応が、会社や職場ですでに決められているなら、その通りに従いましょう。
特に決められていない場合、家族がインフルエンザにかかり、自分が感染しているかどうか分からない状況なら、以下のように対策してください。
・必ずマスクをして、職場でも人との過剰な接触を避ける
・毎朝出勤前に必ず熱を測り、平熱であることを確認する
・熱がなくても体の不調が感じられたら、すぐに病院を受診する
これはインフルエンザを発症していなくても、感染(保菌)しているかも、という考えからの行動になります。
体力があり免疫状態がいいと、感染はしても発症しないことがあります。
しかし、その場合でも体内のインフルエンザウイルスが、ちょっとした咳払いやくしゃみで、飛び散ってしまうことがあります。
そのため、上記のような対応を心がけてください。
保育園・幼稚園・小学生・中学生・高校生・大学生がインフルエンザを発症した場合
・発熱した翌日を1日目として5日目まで出席停止
※発熱した当日は0日目とする
・かつ解熱後2日目まで出席停止
例)発熱したのが2月1日で、2月3日に平熱に下がった場合
2月1日(0日目)→2月2日(1日目)~2月6日(5日目)まで休まなければならない
例)発熱したのが2月1日で、2月5日に平熱に下がった場合
2月5日(4日目)からさらに2日目→2月7日(解熱後2日目)まで休まなければならない
学校がこのようなルールになっているのは、発熱後最低でも5日間、かつ解熱後も2日間は、周りの人にインフルエンザを感染させてしまう(インフルエンザ菌をばらまいてしまう)可能性があるからです。
大人の場合も同じで、無理をして出社することで、周りの人に大きな迷惑をかけることになりかねません。
会社によっては、インフルエンザ時の明確なルールがない場合がありますが、家族がインフルエンザにかかったり、自分がかかった場合は、上記の期間は注意を続けましょう。
抗インフルエンザ薬「ゾフルーザ」について
ゾフルーザは、2018年シーズンから使われるようになった、抗インフルエンザ薬です。
小さめの錠剤で、1回2錠(年齢や体重による)だけの服用で済みます。
薬代は5日分のタミフル錠剤より少々高くなりますが、1回で飲み終わるため、利便性が高いのが利点です。
また、ゾフルーザは体内のインフルエンザウイルスを増殖させない効果があるため、人へ感染させる期間が今までよりも短くなるとされています。
今後、ゾフルーザを服用する人が増えることで、出席(出勤)停止期間が短くなる可能性もあるかもしれません。
まとめ
インフルエンザには「感染」と「発症」の2段階があることを心に留めておいてください。
家族はかかったけど、自分はうつらなかった!という場合でも、インフルエンザウイルスを保菌している可能性があります。
知らず不用意に周りの人にうつさないよう、注意してくださいね。
あとは、日頃から栄養のあるものを食べ、軽い運動などで基礎体力をつけて丈夫な体を保持できるようにすることが大事です。